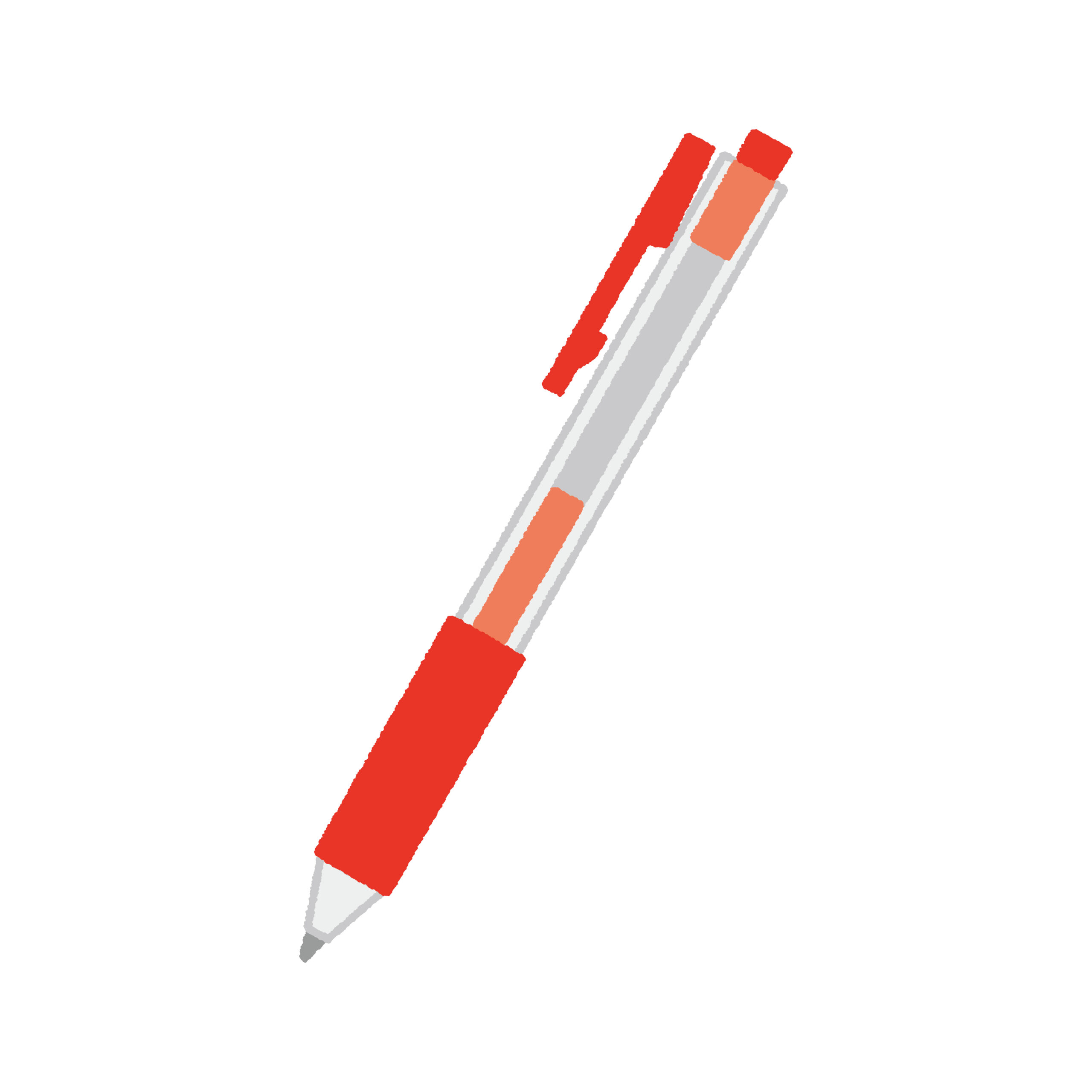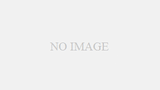急ぎで手紙や書類を送りたいとき、頼れるのが日本郵便の「速達」サービスです。
通常郵便よりも優先的に扱われるため、最短で翌日に届くスピード感が支持されています。
ただ、いざ準備しようとして「赤いマーカーが見つからない!」と困ったこと、ありませんか?
そんな場面で活躍するのが、赤いボールペン。
実は、速達用の封筒に赤マーカーの代わりとして使えるんです。
この記事では、赤ボールペンで速達ラインを引くときの正しいやり方や注意点、ポストから出す場合のポイント、料金の調べ方、郵便局の窓口利用との違い、さらに失敗しがちなパターンまで、2025年7月現在の最新情報をもとにわかりやすく解説していきます。
見落とさないで!速達封筒に必要な「赤線」の意味とは
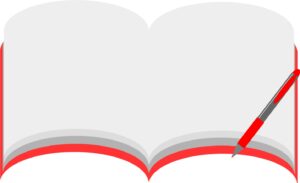
速達で郵便を送りたいときには、「これは急ぎです」と郵便局側に明確に伝わるようなサインが必要です。その役割を果たすのが、封筒に引かれた赤い線。
これが目印となり、郵便物が速達として優先的に処理されるきっかけになります。
一般的には、赤マーカーを使って太めの線を入れるのが主流ですが、マーカーが手元にない場合は赤いボールペンで代用してもOK。
色がしっかり見えるように描けば、速達としての目印として機能します。
筆者の体験メモ
私が初めて速達を出したときの話です。慌てて封筒を準備したせいで、赤線を引き忘れてしまい、結果的に普通郵便として処理されてしまったんです。
届くのが1日遅れてしまって焦りましたが、それ以来「赤線は速達の合図」ということを強く意識するようになりました。
今では封筒の準備をするとき、最初に赤線をチェックするのが習慣になっています。
赤いボールペンでも大丈夫!速達封筒に線を引く際のポイントまとめ

急いで郵便を出したいのに、赤いマーカーが見つからない…そんなときは赤色のボールペンがあれば代用できます。
ただし、見た目のわかりやすさが大切なのでいくつかのポイントを意識して描くようにしましょう。
描くときのポイントまとめ
| チェック項目 | 詳細なポイント |
|---|---|
| 色の選び方 | 鮮やかな赤を使うのが理想。くすんだ赤や朱色は避け、目立つ色を選びましょう。 |
| 長さの目安 | 赤線は4cm以上を目安に。短すぎると気づかれにくくなります。 |
| 太さの基準 | おおよそ3mmくらいが見やすい太さ。細いボールペンを使うときは、2〜3回なぞって線に厚みを持たせましょう。 |
| 本数について | 基本的には1本で十分。ただし、細すぎる線は避け、太く見える工夫を。 |
| 補足アドバイス | 線だけでなく「速達」と赤字で書き添えると、さらに親切です(義務ではありませんがおすすめ)。 |
筆者のちょっとした経験談
過去に、手元にあった細めの赤ペンで線を引いたものの、出来上がりがとても薄くて不安に…。
郵便局で尋ねたところ「見た目で判断できればOKです」と教えてもらい、その場で線を重ね描きして提出。無事に速達として届きました。
それ以来、「はっきり目立つこと」が何より大切だと心に留めています。
封筒の種類で変わる!赤線の入れる位置を確認しよう
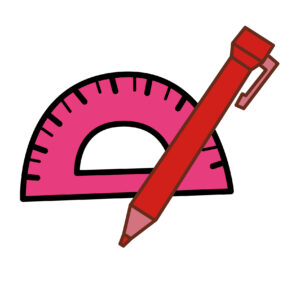
赤線を引く位置は、封筒の形状によって異なります。
基本は「宛名が書いてある表面」に線を入れること。見えにくい位置に描いてしまうと、速達として見逃される可能性があるため注意が必要です。
| 封筒のタイプ | 赤線の正しい位置 |
|---|---|
| 長形(縦長タイプ) | 宛名面の右上に、横向きの線を一本入れる |
| 角形(横長タイプ) | 宛名面の右端に沿って、縦に線を引く |
【2025年最新版】速達料金&郵便料金の確認ガイド|今の金額はいくら?
2024年10月に郵便料金の見直しが行われ、2025年7月現在の送料体系が新しくなっています。
送る物の大きさや重さ、さらに速達をつけるかどうかで必要な金額が変わってくるため、事前のチェックは欠かせません。
■ 通常郵便の基本料金(2025年7月時点)
| 郵送区分 | 重さの目安 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 定形郵便 | ~50g | 110円 |
| 定形外郵便(規格内) | ~50g | 140円 |
| 〃 | ~100g | 180円 |
| 定形外郵便(規格外) | 50g超~ | 260円~(重さにより加算) |
速達をつける場合の追加料金(加算額)
| 重量区分 | 速達料金の追加額 |
|---|---|
| ~250g | +300円 |
| ~1kg | +400円 |
| ~4kg | +690円 |
📌 例:25gの定形郵便を速達で送りたい場合
→ 基本料金110円 + 速達加算300円 = 410円分の切手が必要です。
複数の切手を組み合わせても合計金額に達していれば問題ありません。郵便局の窓口で購入するのもスムーズです。
筆者の体験談:古い切手でも速達は送れる?
昔集めていた1円や10円切手がたくさん余っていたので、それらを貼り合わせて速達郵便を出したことがあります。
貼る数が多くて封筒がちょっと見た目ゴチャつきましたが、金額が合っていればOKとのことで無事に配達されました。
ポイントは、切手をバラバラに貼らず、できるだけ端にまとめて貼ること。
意外と見栄えも大事です。
ポスト投函で速達を出すときの確認事項
速達はポストからでも送れます。ただし、以下の項目をきちんと確認しましょう。
-
表面に赤い線をしっかり入れる(長さ・太さ・位置に注意)
-
基本料金と速達分の切手をきちんと貼る
-
投函時にポストの投入口を確認する(「速達」と「手紙」が分かれている場合あり)
速達専用の差入口が設けられているポストもあるので、その場合はそちらに入れるのがベスト。
もし分かれていない場合は、通常の「手紙」用の投函口で問題ありません。
筆者のうっかり話:速達投函口を見逃した!
あるとき、準備は完璧だったのに、ポストの構造をよく見ずに「普通郵便」の方に入れてしまったことがありました。
それでも赤線と切手で判断されたのか、きちんと速達として届いたのは安心でした。
それ以来、「投函口のラベル確認」は欠かさないようにしています。
郵便局の窓口を使うメリットとは?
速達を確実に処理してもらいたい場合や、ちょっと不安なときは郵便局の窓口を利用するのがおすすめです。
「速達でお願いします」と伝えるだけで、以下のような対応をしてもらえます。
-
内容物を量って、正確な送料を計算
-
必要な金額分の切手をその場で購入可能
-
赤線を引き忘れていても、ラベルやスタンプで対応してくれる
-
受け取りの証明書(受領証)が欲しい場合も発行してもらえる
手書きの赤線に自信がない、切手の組み合わせが不安…という方は、窓口を活用することで安心して送れます。
コンビニから速達を出すときの注意点|失敗しないための事前チェック
ローソンやミニストップなど、一部のコンビニには郵便ポストが設置されており、速達郵便を投函することも可能です。
ただし、どこの店舗でも対応できるわけではないため、利用前にいくつかのポイントを確認しておくと安心です。
コンビニ投函前に確認すべきポイント
-
その店舗にポストがあるかどうか確認を
すべてのコンビニに郵便ポストが設置されているわけではありません。特にセブンイレブンやファミリーマートは未設置の店舗が多いため注意が必要です。 -
封筒のサイズや厚みに要注意
ポストの投入口は限られた大きさしか対応していません。封筒が厚すぎる場合、入らずに投函できないことがあります。 -
集荷時間を事前にチェック
ポストごとに集荷のタイミングは異なります。夜間や午後遅くの投函は、翌日の扱いになってしまうこともあるため、なるべく午前中に出すのがおすすめです。 -
特殊なサービス(書留・配達証明など)は使えません
こうしたオプションを利用したい場合は、コンビニではなく郵便局の窓口に直接持ち込む必要があります。
また、貼った切手の金額や赤線の見え方に不安があるときは、無理にコンビニポストを使わず、窓口で対応してもらうほうが確実です。
筆者の体験メモ
深夜に急いで提出したい書類があり、近くのローソンのポストを利用しようとしたことがあります。
しかし、封筒が少し分厚く、投函口に入らずに困ってしまい、店員さんに相談するはめに…。
最終的には翌朝に郵便局へ持参して手続きできましたが、時間帯によってはこうしたトラブルも起こりやすいので、厚みやサイズの確認は大切だと痛感しました。
速達でありがちなトラブルとその回避法
| よくあるミス | こうすれば防げる! |
|---|---|
| 切手の貼り忘れ・不足で返送 | 郵便物を送る前に重さをきちんと量り、必要料金を確認。差額用の切手も準備しておくと安心です。 |
| 封筒がポストに入らない | あらかじめサイズと厚みをチェック。ポストに収まらない場合は投函できません。 |
| 集荷後に投函していた | ポストに記載された集荷時間を確認し、なるべく午前中に出すように心がけましょう。 |
| 書留を付けられなかった | 書留・追跡付きなどのサービスは、郵便局窓口のみでの対応となります。ポストでは扱えません。 |
色覚配慮。赤線が見づらい場合の工夫とは?
視覚的に赤色がわかりにくい方や、手元の赤ペンの発色が弱い場合でも、速達であることを伝える方法はいくつかあります。
-
赤線に加えて「速達」と文字で明記
視認性が高まり、郵便局側にも伝わりやすくなります。 -
発色が不安なら、窓口での対応に切り替える
色味に不安がある場合は、無理せず郵便局の窓口へ。赤線がなくても、ラベルやスタンプでしっかり速達処理してくれます。
コンビニポストは便利ですが、条件によってはトラブルになることも。
不安な点があるときは、迷わず郵便局の窓口を利用するのがベストです。
スムーズに確実に届けるために、ぜひ事前の確認を忘れずに。
速達とレターパックプラス、どちらが便利?違いをわかりやすく比較!
書類や小包を「できるだけ早く相手に届けたい」と思ったとき、選択肢として挙がるのが「速達」と「レターパックプラス」。
どちらもスピード配送が可能ですが、内容や料金、機能に少しずつ違いがあります。
どちらを選ぶべきか、シーンに応じて使い分けられるように特徴を整理してみましょう。
| 比較項目 | 速達(通常封筒+速達オプション) | レターパックプラス |
|---|---|---|
| 配送日数 | 最短で翌日配達(※地域により異なる) | 基本的に翌日到着(地域差あり) |
| 料金(〜250gの場合) | 約620円(例:110円+速達加算300円〜) | 600円(全国一律) |
| 追跡サービス | 原則なし(書留を追加すれば追跡可) | 標準装備で追跡番号あり |
| 損害補償 | 通常はなし(書留等で追加可能) | 補償なし |
| 差出方法 | 郵便窓口またはポスト投函 | 郵便窓口またはポスト投函 |
💡 使い分けのヒント
レターパックプラスは、送料が全国どこでも同じで、追跡番号も標準でついているため、料金を気にせず送りたいときや配送状況を把握したいときに特に便利です。
補償が必要な場面では、速達に書留オプションをつけると安心です。
速達を出すときの準備チェックリスト
速達を確実に届けるためには、以下のポイントを出す前にしっかり確認しておきましょう。
-
📏 郵便物の重さを量って、必要な料金を把握しているか
-
💌 貼る切手の金額に不足がないか(古い切手を使う場合は差額で調整)
-
✍ 赤線を封筒の右上または右側に、見やすくしっかり描いたか
-
📮 投函方法を確認したか(ポストの場合、「速達専用口」があればそちらへ)
-
🖍「速達」と文字で明記しておくと、より分かりやすく親切(任意)
まとめ|速達は準備がすべて!正しく使って確実に届けよう
「できるだけ早く送りたい」というニーズに応えてくれる速達は、頼りになる郵便サービスのひとつです。
赤マーカーが手元になくても、明るくはっきり見える赤いボールペンで線を引けば問題ありません。ただし、線の位置や太さ、切手の金額など、基本ルールを守ることが前提です。
もし料金に不安がある場合や、書き方が合っているか心配なときは、郵便局の窓口を利用するのが安心です。
窓口では重さを測ってくれるほか、適切な料金案内や速達処理も行ってくれます。
丁寧に準備すれば、速達はとてもスムーズで便利な配送方法です。
用途に合わせて上手に活用してみてくださいね。