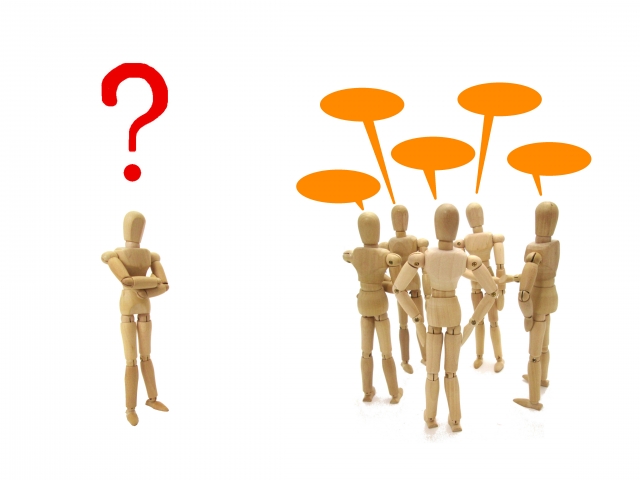子どものころ、一度は耳にしたことがあるはずの「ちちんぷいぷい」というおまじないの言葉。
耳に残るこの独特な響きには、どんな由来や意味があるのでしょうか。
いったいどこで生まれた言葉なのか、そして地域特有の方言なのか──そんな素朴な疑問を抱いたことはありませんか。
世界で親しまれるおまじないの言葉たち
「アブラカダブラ」
世界的に有名な呪文「アブラカダブラ」は、日本でも手品やマジックショー、映画、アニメなどで耳にすることが多い魔法の言葉です。
その起源には諸説あり、アラム語で「私が言うとおりになる」「言葉どおりに消えよ」といった意味を持つともいわれています。
もともとは病気の治癒を願って使われ、お守りに刻むと病を退ける力が宿ると信じられていたという歴史的背景もあります。
「くわばらくわばら」
日本生まれのおまじないで、漢字では「桑原桑原」と表記します。
由来には「雷は桑の木を避ける」という言い伝えや「蚕が桑の葉を食べることから養蚕農家が唱え始めた」という説など、さまざまな説があります。
さらに、平安時代の学者で右大臣まで務めた菅原道真公にも関係するといわれています。
道真公は、宇多天皇から醍醐天皇への代替わりの際、無実の罪で太宰府に左遷され、その地で亡くなりました。
その後、都では度重なる災難が起こり、これが道真公の祟りだと恐れられるようになります。
そんな中、道真公の屋敷があった京都府中京区の桑原地区だけには雷が落ちなかったという話が伝わっており、この出来事をきっかけに雷除けのおまじないとして「くわばらくわばら」ととなえる風習が広まったといわれています。
まとめ
「ちちんぷいぷい」は、本来は子どもの心を落ち着かせたり、気をそらしたりするためのおまじないとして使われてきました。
しかし近年では、その独特な響きがもたらす不思議な雰囲気から、マジックショーやアニメの中で“魔法の言葉”として登場し、多くの人に親しまれる存在となっています。
語源には、江戸時代の徳川家光にまつわる説や、茨城県に伝わる方言「千々乱風(ちぢらんぷう)」が変化したという説などがありますが、どれが真実かははっきりしていません。
それでも、「ちちんぷいぷい」という愛らしく耳に残る言葉には、子どもはもちろん、大人の心にも懐かしさや温もりを呼び覚ます、不思議な魅力がある――筆者はそう感じています。